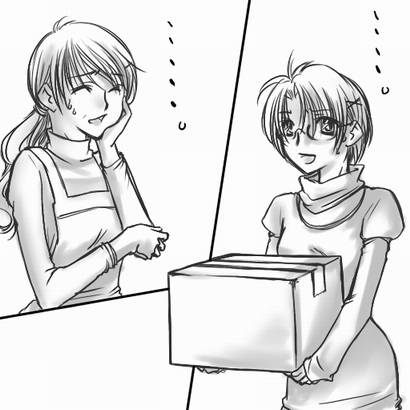その日の夕ご飯前―。
「こんにちは、おばさん♪」
「あら、あずさちゃん。いらっしゃい」
階下で、2人の話し声が聞こえてくる。
耳になじんだはずの声が、一瞬、誰だかよくわからなかったのは、たぶん、意識がハッキリしなかったせい。
現実なのか、それともまだ夢の中なのか―?
どこか虚ろな気分のまま、佐織は寝返りをうった。
「ふわぁ~、あずさが来はのね~」
自然と出たあくびに包まれて、奇妙なつぶやきを漏らしてしまう。
あぁ、ほんのちょっと休憩するつもりだったのに、なんだかウトウトしてしまったみたい。
ころんと寝返りを打った視界に机上の携帯電話が飛び込み、ふと佐織は先ほどのメールに、まだ返事を送っていないことを思い出した。
“今…なにしてる?”
という、短い内容に対する返事を。
まあ正確には、一度メールを打ちかけたんだけれどね。そこでいろいろなことに気がついて、あわてて取りやめて。それでそのままになっていたのだ。
――と。
そこまで振り返って、佐織は一瞬、今すぐにでも起き上がってメールしようかと身構えた。
…のだけれど…。
それだとちょっと変。…というか、慌てて返事をしたのがまるわかりだ。今、すぐそこに迫っているから、とりあえず返事だけしましたよって―。
さて、どうしよう――?
再び横になって、ころころと寝返りを打って。
「うん」
佐織は一人、小さくうなづいて結論を出した。
「とりあえず、放置」
さっくりと声に出して言いきったら、意外とスッキリしてしまった。これで一件落着、みたいな―。
そんなふうに納得してしまったので、佐織はもう少しごろごろすることにした。別に心配することはない。メールの返信が遅れたからって、気まずくなる間柄でもないし。
玄関から2階が吹き抜けになっているからだろうか。聞くともなしに、階下のやりとりが耳に入ってきた。
「兄がみかんを送ってきたので、おすそ分けに来ました」
ドサッと何かを置くような重い音がして、段ボールのこすれる音がする。お母さんのちょっと控えめな歓声が続いた。
「あら、みかん。今度は敬一郎さんかしら? 確か今回はまだ、送ってきていなかったわよね?」
だんだん声のトーンが下がっていくのは、正直言って、あまり嬉しくないから。
どうやらあずさは、みかんを箱ごと持ってきたようだった。
「うへぇ~~…本当に?」
ガックリと枕に顔を埋めたのは、2階の自室にいる佐織。やっと終わったと思った日々が、また戻ってくると思ったら…愕然としない方がおかしいだろう。
それはお母さんも同じらしく。
「あらあら・・・」
困惑以外の何物でもない言葉を発している。
すると、持ち込んだあずさ自身も、その反応は予想済みだったらしく、パチンと手を合わせて懇願した。
「ごめんなさい、おばさん。これで全員だから…。協力して、ねっ?」
「もお…」
沈黙と一緒に、微妙な空気が流れていく。
…というのも、先日。
つまり、2人が旅行に出ていた間のこと。
家人のいない三倉家の代わりに、お隣の神崎家には特大サイズのダンボール箱が次々に届けられていたのだ。
その数、なんと6箱。
差出人はすべて、あずさのお兄さんたちだった。ちなみに彼らは全員で7人いるから、あずさが家を留守にした間に、そのほぼ全員がこぞって送ってきてくれたことになる。
その理由は――あずさが推測するに、こういうことらしい。
「旅行前の電話でね。『風邪が流行ってるから気をつけて』って言われたの。それで私、『大丈夫。風邪予防にみかんを食べているから』って答えたの。柑橘系、好きだし。で、たぶん、こうなったんじゃないかなーと…」
旅行から戻った当日のこと。
出迎えてくれた段ボールの山に圧倒されつつ、苦笑いするあずさの解説を拝聴して、佐織は納得したのだった。
「また、このパターン…ですか………」
…と、カバンを取り落としながら。
まあ、別に珍しい話ではないんだけれどね。
というか、日頃から、こういうことはよくあった。
『元気にしているか?』
『何か欲しいものはないか?』
『どこか行きたいところはないか?』
などなど…。数え上げればキリがない。
ほとんど家にいないお父さんと暮らす妹のために、お兄さんたちは常に妹を気遣い、その望みを叶えようとしてきた。
…なんて、それだけ言うなら、よくある美談で終わってしまうかもしれないけれど、三倉家の場合はちょっとレアなケースで。
お兄さんは7人。
だから、贈り物も7つ届けられるのだ。
そういうわけでこうして、贈り物がかぶってしまうことも少なくない。…というか、かなり多い。
まあ、完全なるご厚意なわけだから、贈られるあずさはいつもニコニコと受け止めているけれど…余波を受けることになる身としては、ちょっとくらいやんわりと断ってくれたらなーと思わないわけでもない。
実際、言えないけれど。
誰も言わないのなら、何かが勝手に変わるということはあり得ない。
そういうわけで、時代は流れ続けて…それが今回は、みかんだったと―。そういうわけなのだ。
「ふう…」
ごく近い未来を想像しつつ、げんなりしながらもあずさの解説を聞いたあと。佐織は落ちたカバンを玄関の上がりかまちに移動させて、2人並んで靴を脱いだ。
「いつもと同じだね」
「そう。同じよね…」
言葉とは裏腹に淀んだ瞳のままで―。
『あぁ、どうするのよ…みかんって、熟すの早いのに!』
なんて抗議したい気持ちを抑えて、顔を上げ、段ボールのふたをあけて中身をのぞきこむ。
無意識のうちに声が漏れた。
「あぁーーー…、ちゃんといっぱい入ってるぅー……」
というわけで、今回も、戦いが始まった。
佐織が旅行の荷物を片付け、いったん家に戻ったあずさも共にすることになった夕食の前―。
ダイニングテーブルで、お母さんが電卓で計算したノルマは、1人15個だった。もちろん、トータルではなく1日の量である、念のため。
「多っ!!」
思わず悲鳴を上げた佐織に、お母さんが壁にかけられたホワイトボードを指し示す。
普段は買い物リストとか、ちょっとした用事が書いてあるのがすっかりキレイにされて、代わりにはぎっしりとご近所さんの名前と、渡す数が記されていた。
「さすが…。おばさん、仕事が早い…」
目を丸くしているあずさに、お母さんが腕まくりして微笑む。
「ありがとう。こういうときのために、ちゃんとリストを作っているからね。お裾分けする人とその個数の比率と。計算が出来上がってるから、すぐに数が出せるのよ」
「さっすがー!」
「うふふ♪」
すっかりその気になっているお母さんに、佐織は挙手した。
「先生、質問」
「はい、神崎さん。どうぞ」
「…って、お母さんも神崎さんじゃない。ま、いいや。ねえ、この計算が完璧なのはわかってるけど…その…やっぱり、1日15個って多くない…?」
「多くないわよ」
ズバッと切り捨てるお母さんに、佐織はなおも食い下がる。
「せめて10個にしない? いや、出来たら5個とか……もっと出来たら1個とか…。その、ねぇ…?」
上目遣いで手を組み合わせて、祈るように見上げる。なぜって、佐織は柑橘系が苦手だから。
まあ、食べれないことはないんだけどね。好んで口に入れるほどでもない。幼稚園児だった頃、冬のとっても寒い日にお風呂に浮かんでいた柚子をかじって以来、ちょっと苦手になってしまったのだ。
そしてそれは、ここにいる2人も知っている………はずなのに。
「15個にしましょう。あずさちゃん?」
「そうしましょ、おばさん」
「え、え、え?!」
動揺する佐織を置いてけぼりにして、ホワイトボードの隅に書き込んでいく。
“家族は1日15個ずつ、食べること”
「ひどいーーー…」
涙目になる佐織をよそに、食後、みかんはきっちり15個、それぞれの前に配られたのだった。
それから数日後の今日―。
ようやく食べきり、配りきり、なんとかみかんバトルから生還した神崎家に、またもや新たな箱がもたらされた、と。
つまり、そういうことなのだ。
「あははははー・・・。ね、お願い。おばさん♪」
あずさの苦笑いが、階下の空気をさらに微妙なものにする。
その足元にはおそらく、段ボール箱があるはずだ。みかんがいっぱい入った7箱目の。
「えーっと・・・」
お母さんが半ば、うなるようにしてつぶやいている。
そりゃあ、いくら柑橘系が好きだからって、正直うんざりするだろう。いや、うんざりを越えて、もはやしんどいと言ってもいいかもしれない。
でも、あずさの家には、ほかに食べる人がいないから。お父さんは仕事で留守がちだし、お兄さんたちは独立してそれぞれの場所に住んでいるし、それにお母さんは―。
「…あ」
ベッドから体を起こして、壁にかかったカレンダーを確認する。
一昨日はあずさの誕生日。そして明日は…確か―。
「おばさんの…」
思い出しかけたことを、階下の物音が吹き飛ばす。
玄関のドアが開いて、数ヶ月ぶりにあの子の声が響いたのだった。
「たっだいま~♪」
次回、”ターニングポイント~5~”に続く