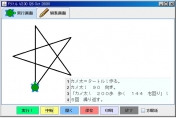タイトルに「バカ」がつく新書をよく見かけるようになりましたが,
最近,こんな本が出たようです。『水と空気とウェブ。』の著者カオスとして無視できないタイトルです(笑;)
このブログ内では本書に関する詳しい感想はあえて書きませんが――書かない理由は本書を読めば判るかもしれません。――,『ウェブ進化論 』がウェブに関する「理想」だとすれば,本書は多くの「現実」を語っています。
仕事や勉強,遊びにウェブが欠かせなくなっている人,ウェブから多くの情報を得ている人,ブログを読み書きしている人など,「ウェブ」に関わっている人にはおすすめの一冊です!