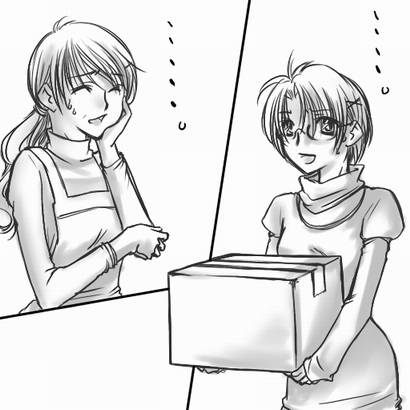踊り場でくの字に折れた階段の下では、3人が依然として立ったまま会話を繰り広げている。
それを見下ろしながら、首をかしげる佐織を残して。
「あずさ、何でシチューだってわかったんだろ?」
すると、まるでその独り言が聞こえていたかのようなタイミングで。
「はい、おばさん」
あずさが曖昧な笑みを浮かべつつ、手首にぶら下げていた買い物袋を差し出す。その態度を一瞬だけ訝しがった後、お母さんは口元をおさえた。
「あら、これ…」
「これ、車庫の前に置きっぱなしにしてあったよ」
受け取りながら、お母さんは口元の手を頬へと移動させる。
「やだわ。さっき車から降ろして、そのまま忘れていたのね」
そういえば―と、階段の手すりに頬杖ついて佐織は思い出す。
『お母さん、さっきまで外にいたんだっけ。お友達に会って買いものに行くとかで』
そう、あれは確かお昼過ぎだったろうか。佐織が資料を読み漁っているとき、玄関から声をかけてきたっけ。
「帰りに夕飯の材料、買ってくるから。あ、今日もドーナツいるー?」
とか、なんとか。
それで佐織は、大げさに顔を引きつらせつつ返事したのだった。
「もういいよぉ~…。これ以上食べたら、ドーナツになっちゃう~!」
ここ何週間か、ずっとドーナツ屋さんに通っていたから。
数週間前の学校帰りに、ちょっと足を伸ばして通りかかったお店で、景品として店頭に出たスケジュール帳に一目惚れしてしまって。
その日からドーナツを食べて、食べて、食べつくして。
そうやってついには家族まで巻き込んで、ポイントを集めていたのだ。
そして無事、お目当ての黄色いそれを手にして…気分はまさに感無量。
『このぶんだと来年はいい年になりそう♪』
そう思いながら、大事に大事に抱きかかえてお店を後にしたのだった。
って……あれ―?
「ん、今何の話してたんだっけ?」
どうやら何分か脱線していたみたい。
またやっちゃった・・・。
話を聞くために、こんなにコソコソしているのに―と、佐織は頭をぽりぽりかいた。
そして当然のごとく、階下の話題は進んでいた。
「ちょっと失礼~」
お母さんの照れ笑いがひと段落したところで、実佐がお母さんの手にある買い物袋を拝借して、中身をチェックしていた。
直後―。
「やっぱりね」
ニヤリと不敵な笑みを浮かべて、買い物袋を返却した。
「やっぱり…ないね、ジャガイモ♪」
その言葉を耳にして、佐織はある感想を抱いた。
『し…しつこい…』
もう終わった話だったと思っていたのに。どうやらまだ、あきらめていなかったらしい。
そんな妹の頭のてっぺんに、“買物”の2文字が浮かんでいるように見えた。
「そうねぇ~…」
お母さんが困ったようにちらりと、靴箱の上に飾られた時計を見る。
実佐のカバンはいつの間にか玄関の上がりかまちの隅に、本人の指先はドアノブにかけられていた。
そのまま体をひねるようにして、上目づかいに輝く瞳を向けてくる。
「ねーぇ?」
瞬間。
佐織は息をのんだ。
「うわ、久しぶりに来たよ…………!」
昔から実佐は、甘えん坊で―…おねだり上手だった。
それもそんじょそこらの女子にはかなわないほどのレベルの―。
「いこーよぉー、おかーさぁん♪」
さすがは、実佐。
町から離れようとも、全寮制の学校へ入れられようとも、ちっとも衰えてなんかいない。
辺りの雰囲気を変え、自分に注目させ、そして望みを叶えさせる”おねだりスマイル”のパワーは―。
あーあー……。
もう、ダメだ。お母さん、ほほがゆるんでいるし。あずさはかろうじて理性を保っているようだけれど、あいかわらず存在感消しているし。
まあ、“人のイベントは蜜の味”な彼女が、騒動(?)の矢面に立ってくれるとも思えないけれど。
現に今も。
「あらら~…」
なんて、優等生スマイル浮かべてるし。
そんな親友に佐織は、
「楽しまないでよ、もう。お夕飯が遅くなるでしょっ?」
と、注意したいけれど、階段の上と下では聞こえるはずもないし。いまさら、降りていくのもちょっと気まずいというか・・・。
久しぶりに会う娘の必殺技に、あっけなくやられてしまったお母さんはほうっとため息をついた。
「もう、仕方ないわねぇ…。30分だけよ? それを越えたら、絶対に帰ってくるわよ?」
30分?
あの実佐を連れて?
ショッピングセンターに行って、帰ってくる?
そんなの無理無理! 絶対ありえない!
だけど。
佐織はうつむいた。
「ジャガイモ・・・・・・欲しいよね・・・」
とろけるようなあまーいシチューに、ほくほくのジャガイモがあるのとないのとでは大きな違いがあるわけで。
お母さんが作ってくれるシチューと聞いたときから、体はもうジャガイモを食べるスタンバイを完了しているわけで。
「ん~~………どうしよぉ~~……」
特に意見を求められたわけではないけれど、佐織はひとり、頭をかかえた。
ここは姉として、妹に注意すべきなのだろうか。
きっちり、しっかり、たっぷりした尊厳を持って。
階段を下りながら、
『実佐、あなたはジャガイモを買いに行ってはいけないのよ』
なんて、歌劇団ばりの発声で雄々しく、美しく降りていった方が―・・・。
「……って、何、そのリアリティのないセリフは~~!?」
考えて考えて結局何も出来なくて。
「うぅ~・・・・・・」
佐織は壁にもたれて、ずるずるとしゃがみこんだ。
尊厳あるセリフなんて、1個も思いつかない。これでもお姉さんなのだ。
久しぶりに会った妹に、そこんとこビシッと言ってやりたい。
でも、だけど―。
と、悩みに悩んでいたところへ再び玄関の扉が開いて、また1人、家族が帰ってきた。
「ただいま戻りましたよ」
ゆったりした優しげな声は…間違いない、おばあちゃんだ。
孫の自分が言うのも何だけど、とても優しくてそれでいて厳しい、素敵なおばあちゃんだ。佐織が将来、こんな人になりたいなーって思うくらいに。
「あら、実佐ちゃん。おかえり」
シワだらけの顔をさらにくしゃくしゃにして、おばあちゃんが微笑む。
こちらは名づけて“癒しのスマイル”―。
年を重ねて得た深みと、慈愛のパワーを持っている。
その中でたっぷりの愛情を向けられて、実佐は必殺技の最中なのを忘れていつも通りの弾けんばかりの笑顔を浮かべた。
「ただいま、おばあちゃん♪」
「あっちは寒くなかったかい?」
「大丈夫。施設はお金がかかっているみたいだから、山奥の割には底冷えもないし」
「そう。それは良かったねえ」
「うん♪」
のんびりしたやりとりに、辺りがおだやかな空気でいっぱいに……なったところで。
「あ、そうそう」
おばあちゃんは何か、ガサガサとビニールの買い物袋のようなものをお母さんに差し出した。
「はい、佐和子さん」
「ま、お義母さん、これは…?」
ガサガサと広げて、お母さんは思わず、あっと声を上げる。おばあちゃんがにこにこと付け加えた。
「お友達のヨネさんちの畑で取れたらしくてね。おすそ分けしてもらったんだよ」
「・・・・・・」
実佐の沈黙が、何かを予感がさせる…。
どうやら佐織の出番はなさそうだ。ゆっくりとその場から離れて、静かに自室に戻る。
そっと閉めたドアの向こうから、お母さんの言葉が響いてきた。
「美味しそうなジャガイモ。さっそく今日の夕飯に使わせてもらいますね」
こうして、実佐の小さな野望は砕けて散ったのだった。
次回”ターニングポイント7”に続く
↓バナーです。