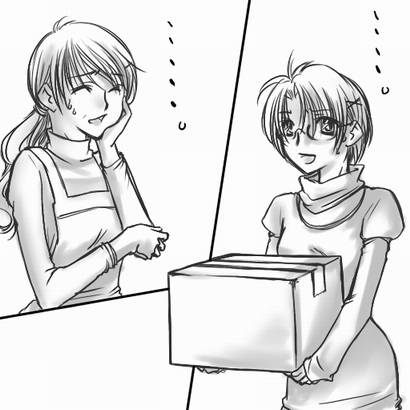「ふぅ…」
いったいもう何度目だろう。
そんなふうにあきれながらも、佐織は1人、また1つため息をついた。
「ふぅ…」
机の上にはめくりすぎて、折り目がくっきりとついたパンフレット。角をそろえて隣に置かれたプリントも、どことなくくたびれてしまっている。
そして佐織はというと、その上に頬杖をついて、窓の外をぼんやり眺めていた。
「まいったなぁ…」
脳裏に、昨夜のことが蘇る。
食後のダイニングテーブルで、実佐からのお土産をつまみながら、あずさはふいに切り出した。
…自分のことを語るの、苦手なくせに。
でもそれすら忘れさせるほどに生き生きと、それでいてちょっぴり緊張しながら―自分の未来について語っていた。
どうなるかはわからないけれど、だなんて前置きして。
でもきっと、そうならないために最善の策を考えているに違いない―そう思わせるような口ぶりで。
彼女が帰ったあと、実佐もずいぶん感心していたっけ。
「やっぱりすごいね、あずさお姉ちゃんって」
って。
でも、佐織はというと。
「う、うん。そうだね」
実佐と同じテンションで話す気持ちになれなくて、あいまいにうなづいていた。
大好きなシチューは美味しかったのに。みんなで食べて、幸せな気分になれたのに。心の中に横たわるもので、消化不良を起こしそうになっていた。
『やっぱり、食べ物だけじゃあ根本的な解決にはならないんだなー』
なんて、当たり前のことを考えたりしていた。
それで―。
あれから10数時間も経た今も、佐織は黙り込んで何かを考えていた。
“目標”、“夢”、“希望”、“将来”、“やりたいこと”―。
昨夜、あずさが語った言葉が、頭の中に散乱している。その1つ1つがありふれていて、耳慣れたものではあったけれど、いまだに現実味がない。
でも…だけど…それってどうなのだろう。5つのうち、1個も答えが出せないなんて…もう18歳なのに。
本当にそれでいいの?
このまま、流れに身をまかせて進んでいってもいいの―?
―と、たっぷり10秒考えて。
ジタバタ足で床を蹴って、佐織は立ち上がった。
「あー、もう知らない知らない知らなーい! 気分転換行くっ!」
何歩か進みきかけてはたと立ち止まり、机の一番下の引き出しを開ける。そっと積み重ねられていた本の下に隠すようにして、資料をしまう。
「これでよしと」
同じことばかり考えていても、仕方がない。
煮詰まった頭の中を冷ますために、佐織は部屋を出た。
トン…トン…トン……
家の中に、佐織の足音だけが響いていく。
床の冷えがしんまで伝わりそうな静けさに、ふと思い出した。
そういえば昨日、お父さんは仕事納めで、今日はお母さんにつきあって年末の買出しへ出かけていったんだっけ。
実佐は、その巻き添えになる前に即座に、ショッピングセンターへ行くことを宣言していた。
「明日は絶対絶対、ショッピングセンターへ行くんだからっ!」
よほど夕方のことが悔しかったみたい。
思い出しただけで、笑ってしまう。
もう、どこまで買い物が好きなんだよって。
「えっと」
頭を切り替えて、ほかの人の予定を思い出す。
えっと、あずさ…彼女は、確か―。
例年通りなら、お墓参りに行っているはずだ。今日はおばさんの命日だから。
おじさんの仕事納めが今日で、お兄さんたちが続々と帰省してきているとか、そんなことを言っていたっけ。
「また年明けに、初詣へ行こうね」
と、約束して。
そういうわけで、あずさに会うのもナシ。
みんなの予定を復習しながら階段を下りきって、佐織はつぶやいた。
「さて、私は何をしよう?」
一応、玄関までやってきたものの、外出しなければならないような用事もないし、そもそも寒いのは苦手だし。だからと言って部屋に戻ったら意味ないし。リビングで見たいテレビ番組もない。
「うぅーん……」
腕組みして、考え込む。
その耳にかすかに、笑い声が届いた。
「?」
くるっと振り返って、階段に沿うようにして伸びた廊下を見つめる。
所々から差し込む陽光の中を、しんとした冷たさが漂う奥で―。
「くすくすっ…」
確かに誰かが、笑っている。
先ほど思い出した各人の予定が、頭に蘇る。
お父さんとお母さんは買出しで、実佐はショッピングセンター、あずさはお墓参り。
―となると、該当者は約1名。
佐織はふわあーっとあくびをして、歩き出した。
まっすぐに進んで、普段、家族3人が住んでいる母屋を抜けて渡り廊下を進んでいく。
はたして声の主は、その障子の奥にいるようだった。
口の中にこもるような笑いと、底抜けに明るい男性のおしゃべり―。
佐織は片手を上げて、軽くノックした。
「おばーちゃん。佐織だけど、いる?」
「はいぃ?」
いぶかしがる返事のあと、男性の声のボリュームがしぼられる。おばあちゃんはそっと障子を開けて、満面の笑顔で迎えてくれた。
「いらっしゃい、佐織ちゃん」
テレビに映っているのは、落語番組だろうか。
そういえばおじいちゃんと一緒に暮らしていたときも、よく聞いていたような気がする。2人して縁側でお茶を飲みながら、季節を愛でつつ、たわいもない話をしていて。
BGMはそう…落語だった。
「どうかしたかい?」
現実のおばあちゃんに話しかけられて、佐織は我に返る。
「あ、ううん。ちょっと考えごとしていただけ」
「そうかい? それならいいけれど」
手招きして、部屋に入っていく。
何を感傷に浸っているんだろう。おばあちゃんがここに住むようになって、もう10年も経つのに。おじいちゃんが亡くなり、それからしばらくして区画整理で住み慣れた土地を離れ、隣の市に住む我が家の庭に、離れを建てて…。
『そうか』
すすめられるままにコタツに足を入れて、佐織は思った。
もう10年経つんだ。
つい最近のことだと思ったのに。
おじいちゃんとおばあちゃんが一緒に暮らしていて、佐織や実佐はちょくちょく遊びに出かけていって。
時間の経過を思い知って、佐織はまた目を伏せる。
京都から戻ってきてからというもの、こんなのばっかり。気分転換をしに来たのに、またこんな…勝手にひとりで凹んじゃって。
『あー、こんなことだから、あずさに言われるのよ』
頭を抱えて、彼女の言葉を思い出す。それに、あずさでない別の人の声が重なった。
「妄想特急・佐織号…だったかね?」
「え!?」
驚いて見上げると、部屋続きの簡易キッチンから、おばあちゃんが戻ってきていた。
「いや、ね。あずさちゃんからそう聞いていたものだから。それにしてもすごい名前だねえ。妄想だけでもすごいのに、特急だなんて。ねえ?」
向かい側に座り、身を乗り出してくるおばあちゃんに、佐織はちょっと戸惑う。
「ど、同意を求められても困るんですけど…。あずさってば……」
指先で、コタツに“あずさ”と書いていく。1個、2個、3個……。
そうこうしている間に、湯飲みが並んで―。
ゆっくりと急須を傾けてお茶を淹れながら、おばあちゃんは嬉々として尋ねた。
「特急は一番早いんだろう。カッコいいねえ。ハイカラだねえ」
まったく何を言っているんだか。
丸い木製の菓子入れからお煎餅を取って、ばりっと噛み砕く。
まあ、そういう、孫と一緒の目線で楽しんでくれるところが好きなんだけれどね。でも正直、あだ名を褒められるのはなんというか………ちょっと違う気がする。
「えーと…。そのー…」
次の話題を探しながら、お茶をすすって、ウロウロと視線を惑わせて。
「なんでもない」
あきらめて、ゴロンと横になった。
カチ…コチ…カチ…コチ…
壁掛け時計が、時を刻んでいく。
佐織は目を閉じて、そのゆっくりしたリズムに身を任せた。
~次回”迷いの中で~2~”へつづく~
↓三倉あずさのラフスケッチ・決定分~その1~