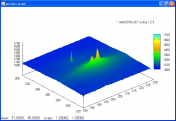ガリレオといえばこれです。ピサの斜塔(KCGIのある先生提供)の上から軽い球と重い球を落として地上に同時につくことを公開実験した(もっともこれは後世の作り話らしい)。それまでの思い込みを実験で打ち破ったのです。落体の実験はなんども行い「慣性の法則」を発見します。天体観測に限らず、実験して客観的なデータをとるという手法は彼が初めてです。なんでもかんでも過去の権威や神様に頼るのではなく、自らやってみること。これこそパイオニアスピリットですね。2003年KCG40周年のときパイオニアスピリットの持ち主としてコロンブス,アインシュタイン,ライト兄弟をあげました。いずれも新領域を切り拓いた偉人ですが,ガリレオこそそれにふさわしく,われわれの範とすべき師です。 以下事項
月別アーカイブ: 2007年12月
明治5年12月3日
わが国で太陽暦が採用されたのは明治6年(1873年)からとなっていますが、正確には旧暦の明治5年12月3日が新暦(現行暦)明治6年の1月1日に変わりました。したがって明治5年は2日のみで、この年には本日12月3日はなかったのです。
暦を変更するために詔書(なんと朕惟フニで始まる)および太政官布告が出ています。しかし混乱を避けるため官暦(政府が正式に認めた暦)にも明治42年の暦まで旧暦の日付が参考として記されていたそうです。
そこで今日はカレンダーの日というらしいが知名度はほとんどゼロ。一方奇術の日でもあるそうな。なんでかって?そりゃ 1,2,3だから。
世界天文年2
ガレリオさんのプロフィール。1564年- 1642年で,シェークスピアと同い年,加藤清正よりひとつ年下で、結構長生きしています。彼の業績は何といっても地動説のプロパガンタですが、その根拠には多数の天体現象の発見があります。月面のクレータ,金星の満ち欠け,太陽黒点,天の川は無数の星の集まり,そして最大の発見は木星の4衛星です。これらは自作の望遠鏡による観測結果で1610年に発表しますが望遠鏡を自作し観測を始めたのは前年の1609年・・・世界天文年はこの年から400年と決められました。彼がローマ法王庁から迫害を受けたのはずっと後で、この頃は問題にならなかったようです。当時は ピサ大学教授(数学・天文学担当)兼トスカーナ大公付哲学者(要するに大貴族のお抱え学者)という肩書です。
彼はもともと医者になろうとしてピサ大学に入学したけど,方向転換して、ユークリッドやアルキメデスを学んだそうです。 以下次項
世界天文年1
再来年はガリレオ・ガリレイが自作の天体望遠鏡で初めて天体観測をおこなった1609年からちょうど400年にあたります。人類が宇宙へ大きく近づいた記念すべき年として「世界天文年2009」とすることを、国際天文学連合が提案し、ユネスコも賛同しました。世界中で色々なイベントが企画されていますが、プレイベントはすでに始まっていて、来年からは盛りだくさんになります。本日、天文教育研究会世界天文年2009WGに加入しました。京都でできることはないか、これとKCG45周年を引っ掛けて来年は何かやろうと考え中・・・
ガリレオさんはPioneerSpritの元祖みたいな人です。今ではアタリマエですが、実験・推論・法則という方法論を始めて、科学というジャンルを切り開いたのですから、しかも抵抗勢力と戦いながら。現在われわれがIT文明を享受できているのもカリレオさんのおかげです。
世界天文年2009
師走,いやまだ神無月
12月になりましたね。もう1ケ月でお正月、師走の風が吹くと言われますが、師走とは旧暦で使うことばです。今日は旧暦では10月22日、だからまだ神無月なのです。旧暦と現行暦をごっちゃにして使うことはよくありますが,気になってしかたない。師走になるのは来年の1月8日から、そのころが教師にとって最も走らねばならない時期ですね。