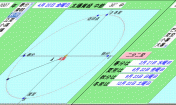前回の桜と同じことですが,暦の中に○○の節句という古くからの年間行事がありますね。
3月3日 桃の節句
5月5日 端午の節句
7月7日 七夕
9月9日 重陽の節句(菊)
ところが3月初にはまだ寒く、桃の花は咲いていません。7月7日は梅雨のさなかで星は見えません。9月9日はまだ残暑中で菊は咲いていません。本来これらの行事は旧暦で行うもので1ケ月半ずらすとちょうどいい季節になります。もっとも近年の温暖化のせいで合わないものもありますが。
「こよみ」カテゴリーアーカイブ
さくら さくら 弥生の空は
さくら さくら 弥生の空は 見渡すかぎり
霞か雲か 匂いぞ出ずる
いざや いざや 見にゆかん
3月に日本中に桜が咲くようになったのは、近年の温暖化のせいであり、桜花満開は4月の入学式につきものです。この歌は明治からずっと小学校で歌われてきているが、みんな違和感はなかったのでしょうか。
実は弥生は3月ではなく旧暦の三月なのです。現行暦では4月中旬~5月中旬ですからちょうどいい。この歌は旧暦時代に作られたのでしょう、きっと。
処暑
8月は小の月だった
7月8月と大の月が続くのはナゼでしょう?実はもともと偶数月はすべて小の月だったのを、ローマ初代皇帝のアウグスツスが、自分の誕生月である8月が小の月であるのが気に食わなくて、1日ふやしたそうです。そのため9月以降の大小がズレたという話です。勝手な話ですが、そのおかげで夏休みも冬休みも1日多い。
元をいえば、ローマの暦はMartius(March)から始まっていて、閏年の調整は最終月で行っていました。その名残はSeptemberは7、Octoberは8、Novemberは9、Decemberは10に関連した言葉ですね。ローマの古暦を改訂したのはアウグスツスの伯父であるシーザーで、彼はエジプト遠征から、暦とクレオパトラを連れて帰ったそうです。
水無月? 弥生?
本日8月1日は旧暦では六月(水無月)十九日ですが,なぜ六月を水無月というのでしょうか?六月は梅雨の時で水は溢れてるはずなのに・・・というのは現行暦で考えるからで,旧六月とは今で言うと7月中旬~8月中旬,梅雨は明けてまさに水不足のころです。
「さくら さくら 弥生の空は・・・」と歌っても3月ではまだ桜は咲いていません(去年は温暖化のため特別早かったが)。この「弥生」は旧暦の三月,現行暦では4月中旬以降です。こういう例はまだまだありそうですね。
暦雑学・・・土用
土用丑の日
暑ぅ,梅雨のうっとうしさが残っていて蒸し暑い毎日です。暦の上では今は土用のさなか。先週の月曜23日が大暑で,明日30日は「土用丑の日」です。今年は1回だけですが,昨年も来年も2回あって,それは決して珍しいことではありません。
土用丑の日といえばうなぎですが,この習慣は江戸時代に平賀源内が鰻屋から商売繁盛を相談されて、発案したとか・・・さすが奇才の蘭学者,経営コンサルタントもやっていたようです。ところが、真夏に鰻を食べることは古く奈良時代からあったらしく、こんな大伴家持の歌が万葉集に載っています。
石麿さんにうなぎを食べるよう勧めている家持さんは医療コンサルタントみたいですね。