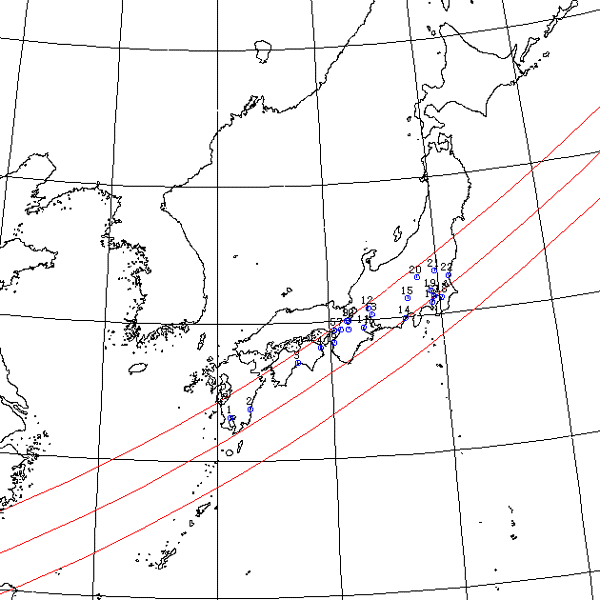「記録は破られるためにある」という名言がありますね。世界新記録はどんどん破られているから、面白い。イチローでも宇宙でも同じです。最も明るい星が、最も遠い銀河が、最も地球に似た惑星が・・・毎年見つかっています。それらは未知への挑戦の成果です。
しかしこの度は。多少事情がちがう。ありえないと思っていたことが起こったのです。
星の限らず、建物でも動物でも、自らを支えるための質量上限があります。すなわちある重さになると自分で支えられなくなって、つぶれてしまうのです。ゾウやカバはそろそろ限界体重ですね。星の場合は大爆発を起こしてブラックホールやパルサーになったりします。今回の超新星の明るさからすると爆発前の星の質量はチャンドラセカール限界という値を超えてしまう、これはえらいことなのです。
何かがおかしいのか?
「限界」以上に輝いた超新星
「星々」カテゴリーアーカイブ
☆今日の土星
2009年9月4日 土星の環が消失
今日は土星の環の消える日。といってもなくなるわけではありません。土星を真横から(エッジオン)でみる状態になるのです。土星の環の厚みはわずか1km程度で、どんな大望遠鏡でも見えません。土星は約30年で公転するので、こういう現象は15年に1度は起こります。
でも環のない土星なんて、味噌のない味噌汁、わさびのきかない寿司みたいなもの
☆旧七夕
今日は旧暦の7月7日、七夕です。天の川を見上げるにはいい季節になったけど、曇って星は見えそうもありませんね。
ところで今朝の読売新聞2面の隅に小さな記事がありました。
古今集に紀友則のこんな七夕の和歌があるそうです。
天の川浅瀬しら波たどりつつ 渡りはてねば明けぞしにける(古今177)
その意味は
「彦星が織姫に会いに行くため天の川の浅瀬を探していて、どこか知らないので白波を辿っているうちに、渡り切れずに夜が明けてしまった。」
なんですがそれは表で、裏の奥では
七夕の宴で天皇から七夕の歌を詠むよう命ぜられ、苦労するうちに夜が明けてしまった藤原の某さんをからかっているそうです。
和歌、特に平安鎌倉時代にはこんなのが実に多い。
関西人によくある隠語、ダジャレの源流みたいな気がしますね。
紀友則の最も有名な歌は
ひさかたの光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ
ですが、これもなんとなくアヤシイ。のどかな春の日に桜の花が散る、その後は藤の季節が来る、いやだなぁ
という意味のとれませんか。藤原氏にいじめられて潰された紀氏のささやかな抵抗。
やっぱり文章表現力はいつの世も重要です。
☆日食観測報告会
本日、京大理学部構内で花山星空ネットワーク主催の日食観測報告会が開かれました。参加者はおじさんおばさんが多かった(5月の準備会では小学生がたくさんいたが)。
トカラ、屋久島、奄美、中国、硫黄島海上へ行った人からのレポートがありましたが、きれいな画像が撮れたのは5番目のみ。でもみなさん、当初の目的は達せられなくてもそれ以外、それ以上の成果を挙げられたようでした。
最後にcastorは今後の日食について話しました。上図は2012年5月21日の金環食を比叡山頂から琵琶湖とともに眺めようというもの。近場でオススメです。
また下図は来年7月にイースター島で起こる皆既日食、実はすでに満杯だそうです。
☆星座の中の動物-2
おひつじ座の羊は全身金色の毛を持ち,空を飛ぶことができます。
フリクソスとヘレという幼い兄妹を継母から救い出し、ギリシアからコルキス(黒海東岸今のグルジアあたり)まで連れて行きました。途中ヘレは海に落ちてしまいますが。
ところがその金毛のお羊は感謝のしるしとして神へ捧げられた(すなわち生贄とされた)そうです。カワイソー!納得できんなぁ。
ギリシアの神様もユダヤの神様も羊が大好物のようで、子羊の焼肉を神へ捧げる場面はよくありますね。彼らにとってはカワイソーではないのかもしれないが・・・。
羊は犬と並んで最も古い家畜だそうです。中国北部からヨーロッパにかけては約1万年前から飼われていますが、日本では明治以降のようです。ヒツジは非常に食べ物に貪欲で、草に根まで食べるそうで、そのため牧羊地は移動していきます。すなわち自然破壊をやらかしてしまいます。わが国では牧羊の習慣がなかったので、森が守られたという話を聞きました。羊を飼う地域は米作ではなく乾燥した麦作地域です。
マトンはパンや麺と一緒に食べるもので、ジンギスカン・ライスというメニューは本来ありえないものですが、そこはいかにも和(日本)的です。
☆星座の中の動物-1
星ネタというより動物怪物のお話で、どう展開していくかわかりません。
しし座のししはギリシア北部ネメアの谷に人食いライオンで、怪力の英雄ヘルクレスに素手で絞め殺されてしまったと言われています(まさか!)。
でもほんとうにギリシアにライオンが棲んでいたのでしょうか?ライオンはアフリカの草原の動物と思いがちですが,インド西部の森に少しだけ残っています。この種はかってはペルシアから小アジア辺りにもいたようです(東アジアは虎の縄張りのためいないみたい)。さらにその仲間であるヨーロッパライオンはスペイン、南フランス、イタリア、そしてバルカン半島の南で1世紀ごろまで生息していたそうで、絶滅の原因は生息地の開発、野犬との競争、過剰な狩猟のせいです。ライオン狩りはコロッセオで闘獣士と戦わせるため、ギリシア人やローマ人にとって必要な仕事でした。
となるとやっぱりギリシアにもライオンは棲んでいた、そしてライオンの谷へ追放という刑罰があったのでしょうね。
☆浦嶋物語-3
前述の『丹後風土記』の中で最も重要な箇所は彼を出迎えた子供たち、昴星と畢星ことこです。昴とは言うまでもなく,すばるのこと、おうし座の散開星団プレアデス410光年の彼方にあります(写真)。古事記にも枕草子にも谷村新司の歌にもあるあの星々のこと。
また畢とはやはりおうし座の散開星団ヒアデスのことで,140光年の距離にあります。なんと蓬山(=とこよ國)とは宇宙の彼方にあったのです。彼は海の彼方の大きな島または海底にあるという龍宮城に行ったのではない!
さあそうなると、往復の手段は超高速の亀型宇宙船となります。出発の時期は雄略天皇二十二年すなわち478年、帰還は二百数十年後の飛鳥時代(後述),ところが彼の中の時間経過はわずか3年,明らかに相対論的効果です。まさにウラシマ効果を体験したのです。:::ウラシマ効果という言葉は誰の発案かわかりません(いろいろ聞いてみたけど)。しかし超高速飛行では時間経過が遅くなるという一般相対論の重要な結論を表現するには適切な言葉です・・・日本人以外には理解できないけど。
☆歴史の中の天文こぼれ話
宇宙からのメッセージ―歴史の中の天文こぼれ話
非常にマニアックな本です。著者は国立天文台名誉教授でもともと太陽の専門家ですが、定年退職後に「古天文学」という新ジャンルを開拓したというパイオニアです。一度お会いしたかったけど、数年前に亡くなられました。
ヒミコ日食あれこれ、信長と朝廷の天文官との争いなどなど面白い話があります。また古代中国では火星は不吉な星とされ、その運行は注目されていたそうです。そのなかで重要なのは、漢の高祖・劉邦の没年BC195年の天象でしょう。この年火星は年初から7月まで,てんびん座でうろうろして,8月初にアンタレス最接近します。病に伏した劉邦は「四月甲辰に崩じた」と記されていますが,この日は干支をもとにして求めると6月1日に当たります。漢の歴史官・天文官にとって初代皇帝の死には天からの予告があってしかるべきと考えたのでしょう。
ところがその15年前(BC210年)にも火星は似たような運動をして、なんともっと大物が亡くなっているのです。その名は、始皇帝、ただし『史記』には没年の前年 始皇三十六年(=BC211年)の天象と書かれています。これは単なる記載ミスなのでしょうか?それとも現王朝の創立者と前王朝の暴君とが同じ天象のもとに亡くなったとは書きにくかったので司馬遷は故意に1年ずらしたのでしょうか?・・・この部分は著者ではなくcastorの推測。
☆日食余話6
夜でも日食は起こるのか?もちろん起こります、ただし見えません。地球の裏側に行けば昼間だからみえます。来年7月11日は南太平洋で。
日本国内では26年後まで、京都では30世紀まで観られないけれど、☆日食後記 | ほしぞら.・古代史・コンピュータ に書いたように日食は毎月起こっています。月の影がどこに落ちるかだけのことですね。
金環食は皆既食のようにコロナやダイアモンドリングは現れないので、見劣りすると言われますが、そうでもないでしょう。3年後5月21日の朝の金環食を見るには東が開けた所がいいですね。下図のように南紀~東海~房総。静岡あたりから富士をバックにするのがいいようですが、比叡山頂ではどうかな?
日食ネタもそろそろ尽きたのでここらで終わります。ご愛読ありがとうございました。
☆日食余話1
このたびの日食でいろいろな質問がありましたので、そのうちのいくつかを紹介します。
中には答えられなくてこの3連休に調べまくったものもあります。
世界最古の日食記録は?
日本最古の日食記録は?
日食時にはどのくらい暗くなるの?
金環食と皆既食のちがいは?
ヒミコの日食はいつ?
安倍晴明はホントに皆既食を見たの?
源平合戦の時の日食はどうなったの?
京都での次の皆既食はいつ?
夜間でも日食は起こるの?
ーーーーなどなどーーーー
日食時にはどのくらい暗くなるのかは、あの通りほとんど変化ありませんでしたね、8割欠ける程度では。真っ暗になって星が見えるのはやはり皆既時だけ、暗くなったのがわかるのは9割以上でないと無理みたいです。でも51年前(子供のころの記憶であてになりませんが)、1958年4月19日には85%の日食でしたが、周りがうす暗くなった。でもその日はとてもよく晴れていました。昨日のような曇天なら、変化はわからないようです。ということは気づかれず、記録されなかった日食はたくさんあったということですね。