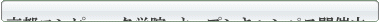ふたご流星群を昨日,大学院で観測しました。天文同好会の学生とたのしみました。
夜中の2時。ふたご座が天頂にあります。いくか流れ星が見えました。百万遍校舎の屋上はいいですね。夕食は写真の通り。天文同好会学生は大喜び。
観測に必須なのはスマホの星座のアプリ。左はiステラHDです。右は星座表。これらのアプリのおかけでふたご座の位置も木星も確認できました。
月別アーカイブ: 2013年12月
21世紀のラッダイト運動がおきました。
産業革命以来ですがラッダイト運動がおきました。
以下のような記事があります。
【参考】
アマゾン、欧州で反発 ドイツ、賃上げ求めスト フランス、無料配送に批判 :日本経済新聞
【ブログ内参照】
機械との競争=テクノロジー失業の襲来 | オブ脳@kcg
日本人は勉強が得意な人が多いのに知的好奇心が低くないですか?
以下のような記事があります。
【参考】
データえっせい: 成人の知的好奇心の国際比較
要点は以下の通りです。
1 日本の成人の知的好奇心は,他国と比して高くないようです。
2 日本は,数学力はトップですが知的好奇心は下から2番目
3 日本の20歳の好奇心は,スウェーデンの65歳とほぼ同じ。2つの並んだグラフをみると驚きますよ。
実は,子供のころからずっと思っていたことですが,勉強がよくできるのに,知的好奇心がない人が多いなあということです。京大に入学して思ったんですが,理学部に来るような人は知的好奇心の旺盛な人が多いですね。研究者志向の人だからでしょうね。
でも,幸いにしていうよりもFacebookの私のお友達は,知的好奇心が旺盛な人が多いので楽しいです。知的好奇心が低くお勉強が得意な人が多い日本は今後どうなっていくのでしょうか?
さて,この記事に対して,ある先生は,「日本人がイノベーションを生み出せないことと関係あるのでは」と言っておられます。
図式化すれば
同じことを繰り返すことに勤勉=日本人
別なことを探すことに勤勉=欧米人
ではないでしょうか。
MathML その13 Matype 6.9
MathMLの記事のまとめておきます。 MathML その11 Mathematicaとの連動 | オブ脳@kcg MathMLその12 MathTyp 6.8が64ビット対応! | オブ脳@kcg
機械との競争=テクノロジー失業の襲来
MITスローン・スクールのデジタル・ビジネス・センターのエリク・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィーの”Race Against The Machine(機械との競争)”は「飛躍的に能力を拡大していくコンピュータに人間はますます仕事を奪われる」といっています。本書によると,リーマン・ショック後,世界的な経済危機は脱しても一向に失われた雇用が回復しない状況に経済学者は頭をひねってきました。第一に,ポール・クルーグマンが唱える景気循環説では,雇用の回復が弱く,需要が不足していると見ています。第二には,タイラー・コーエンが提唱する技術革新の停滞説では,経済を進歩させる新しい強力な発想が生まれてないからだと見ます。彼らは第三の説として「技術の進歩が速すぎて起きる雇用喪失説」の立場をとります。端的に言えば,コンピュータとの競争に人間が負け始めていることこそ,雇用が回復しない真の原因であると主張するのです。 「機械に雇用が奪われる」というこれまでにもありましたが,「単純労働者の雇用がなくなるから知的労働に従事する必要がある」というものでした。知的労働者でも,弁護士などの法曹界や医療診断分野も,コンピュータに浸食されつつあり,そして,eラーニングを始めた大学では講義を簡単に制作して,しかも簡単に配信できるという情報通信技術の進歩は,大学教員や大学そのものの存続を危うくするのです。機械翻訳の精度も上がっているので,海外のコンテンツも日本に入ってきます。
【参考】
名著で考える「人機一体の経営」 – 『機械との競争』、コンピューターが人の仕事を奪う日も近い:ITpro
「中国化する日本」を読んで,欧米以外の大国に目を向けよう!
日本の大学のアカデミズムは西洋から取り入れているので,バリバリの西洋文化なんですね。私自身もアメリカやヨーロッパへの漠然とした憧れから大学院生のときにはサイエンスをやっていました。
ところが,40を過ぎて,はじめて中国大陸に8か月も住む経験を得たことはとても貴重でした。日本語の上手な法学部の先生と話す機会があったことはとても貴重でした。
・中国では家族・親族のネットワークで,サラリーマンをやっている一族が起業する親戚に投資する
・中国の政治体制は一党独裁で,日本の自民党と同じ(ええ?)
・政府と人民はなんの関係もない(それって国家なの?)
欧米思想の「西洋化」,「近代化」,「民主化」の枠組は中国では当てはまりません。しかし,家族・親族のネットワークによって,失業問題を食い止めていることは確かです。中国人が宋の時代から獲得してきた知恵のようです。この知恵を理解すると,人民は家族・親族に頼り,政府に頼らない体質になります。だから,政府が異民族である元や清でも人民にとっては,「そんなこと知ったもんか」となります。アニメの「コードギアス・反逆のルルーシュ」の中で,日本が中国をお金で買収するという部分があります。中国共産党にお金を積めば,日本国政府が中国を買うことすら可能だと暗示しています。中国について理解が進むとありうる話です。まったく欧米の思想なんか通じません。
さらに,「中国は宋代に近代が始まり、都市市民社会をベースにしたメリトクラシー(実力主義)の国になった」という旨が本書に書かれています。欧米思想に染まっている日本の大学教員にはまったく理解不能でしょうね。中国の共産主義はマルクス主義ではありません。毛沢東主義です。また,福州市の大書店に行けば,アダム・スミスの「国富論」が山積みで売られています。驚きですね。大資本家もいます。
中国政府は政治には口出すが,経済活動に関与しないんです。政経分離です。これこそが中国化です。
さて,日本も中国化するといっていますが,中途半端に欧米思想にそまった日本が中国化するかどうかは疑問です。
実は,この本は,京都放送のラジオで知ったんです。こんな本を紹介していたのには驚きです。
ついでながら,中国に行って,留学してきた日本人をみてわかったことですが,中国に興味を持つ日本人は欧米にはあまり興味をもちません。日本にいるアメリカかぶれの人や欧米に興味を持つ人(日本の大多数のアカデミアン)は中国には興味をもちません。特にアメリカに留学したことがある人は,アメリカが世界の常識みたいになりますね。残念ながらそういう方は本書を読んでも「なるほど」とは思わないでしょう。
では本書を読む価値はどこにあるのか? 今後の新興国が西洋化・民主化を経ずに近代化を達成する可能性があると私は考えているからです。新興国の未来を考えていく上においても,この本はある種の予測だと私は考えています。
【目次】
はじめに 新たな歴史観としての「中国化」
第1章 終わっていた歴史―宋朝と古代日本
第2章 勝てない「中国化」勢力―元・明・清朝と中世日本
第3章 ぼくたちの好きな江戸―戦国時代が作る徳川日本(17世紀)
第4章 こんな近世は嫌だ―自壊する徳川日本(18~19世紀)
第5章 開国はしたけれど―「中国化」する明治日本
第6章 わが江戸は緑なりき―「再江戸時代化」する昭和日本
第7章 近世の衝突―中国に負けた帝国日本
第8章 続きすぎた江戸時代―栄光と挫折の戦後日本
第9章 「長い江戸時代」の終焉―混乱と迷走の平成日本
第10章 今度こそ「中国化」する日本―未来のシナリオ
おわりに ポスト「3・11」の歴史観へ
【ブログ内参照】
清朝とは何か | オブ脳@kcg
近未来の途上国がわかる「2033年 地図で読む未来世界」 | オブ脳@kcg
教育未来学 | オブ脳@kcg
『暴走する「世間」で生きのびるためのお作法』を読み直す
この本の書評を以前書いたのですが,再度追加します。
【ブログ内参照】
暴走する「世間」で生きのびるためのお作法
まずは,この著者が日本世間学会を設立していたことが判明しました。
日本世間学会 – The Japanese Sekengaku Society
さらに,面白い書評も発見。ドイツ在住の日本人が書いています。
面白い部分を抜き書きしましょう。
「世間」と「社会」は違います。ヨーロッパにも「世間」はあったらしいのですが,800年ほど前のキリスト教の支配のときに否定されて「社会」に変わったそうです。ヨーロッパでは都市化の要素も加わり,新たな「社会」という人的関係が生み出され,個人が形成されたという。日本ではそうした「社会」とは異なる「世間」という人的支配が続くのですね。
世間は「本質的にいえば、三人以上の関係において存在する共同幻想、つまり複数の人間が持つ共同観念で」(p19)
社会は「バラバラの個人から成り立っていて、個人の結びつきが法律で定められているような人間関係」(p17)
私は、恋愛とは「自分では絶対に制御できないような他者との出会いによって、ボロボロになることだ」と思っている。あるいは,「話せばわかる」とかいったような,一切の民主主義的な努力が報われない世界であることが,恋愛の経験であると思っている。(p.111)
【目次】
第1章 「世間」のオキテを見極めよう―KYとは何か
第2章 学校のお作法―「プチ世間」の登場
第3章 お仕事のお作法―「お世話になっております」の不思議
第4章 ケータイのお作法―即レスの圧力
第5章 恋愛のお作法―「結婚しなくていいですか」の正論
第6章 信心のお作法―お盆とクリスマスが同居する謎
第7章 格差社会のお作法―「妬み」の構造
第四の波 その13 ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代
第四の波「ハイ・コンセプト」に関して,KCGブログも新しくなったので,まとめ直します。まず,この本はアルビン・トフラーの「第三の波」以来の力作です。しかるに,日本でははやっていません。「プレゼンテーションZEN」など,本書を元にした著書も生まれています。この本の内容は,人類の将来を暗示ではなく,明示しています。以下のリンク集を見てください。 英語Kindle版
英語原著版 日本語版 ドイツ語版 【目次】 第1部 「ハイ・コンセプト(新しいことを考え出す人)」の時代(なぜ、「右脳タイプ」が成功を約束されるのか これからのビジネスマンを脅かす「3つの危機」 右脳が主役の「ハイ・コンセプト/ハイ・タッチ」時代へ) 第2部 この「六つの感性」があなたの道をひらく(「機能」だけでなく「デザイン」 「議論」よりは「物語」 「個別」よりも「全体の調和」 「論理」ではなく「共感」 「まじめ」だけでなく「遊び心」 「モノ」よりも「生きがい」) 第四の波 その1 | オブ脳@kcg 第四の波 その2 | オブ脳@kcg 第四の波 その3 | オブ脳@kcg 第四の波 その4 | オブ脳@kcg 第四の波 その5–A Whole New Mind Audio Book | オブ脳@kcg 第四の波 その6 ビデオ発見! | オブ脳@kcg 「第四の波」 その7 中国語版 | オブ脳@kcg 第四の波 その8–プレゼンテーションzen | オブ脳@kcg 第四の波 その9 中国語版を入手 | オブ脳@kcg 第四の波 その10 | オブ脳@kcg 第四の波 その11 | オブ脳@kcg 謹賀新年,第四の波! その12 | オブ脳@kcg